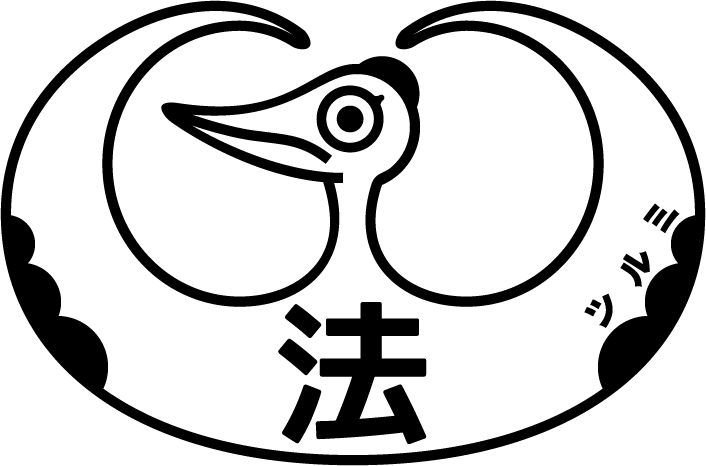使用者から被用者への求償
もちろん、加害者である従業員が、一切お金を払わなくてよいというわけではありません。使用者は、被害者にお金を支払った場合、加害者である従業員に対して、支払ったお金を請求できます。これを求償権の行使といって、民法715条3項に規定があります。
結局、従業員が支払うことになるなら、使用者責任なんて、あってもなくても同じではないかと考える人がいるかもしれません。確かに、算数的な勘定は全く同じです。しかし、現実世界では、大きく結果が異なるのです。
従業員の行為により、1000万円の損害を受けた被害者がいるとしましょう。従業員が1000万円を持っていれば問題ありませんが、持っていないこともよくあります。そんな場合、従業員への請求は無意味です。しかし、会社に1000万円を請求できれば、被害者は泣き寝入りをせずに済みます。会社は従業員に1000万円を請求できますが、従業員が一文無しなら、会社が泣き寝入りすることになります。
つまり、従業員が無資力であるリスクを、被害者に負担させず、使用者に負担させるのが、使用者責任の規定なのです。
使用者から被用者への求償の制限
ここまでは、使用者が被害者に賠償した場合、その賠償金の全額を加害者たる従業員に求償できるという前提で話を進めてきました。民法715条3項も、そのように理解するのが素直でしょう。
ところが、最高裁判所は異なる判断を下しています。つまり、使用者が1000万円の賠償に応じた場合でも、従業員に1000万円全額を求償することはできないと判断しているのです。
その根底には、やはり報償責任という価値判断があります。また、使用者は、損害保険に加入したり、発生しうる事故のリスクを商品の価格に転嫁したりしておくことも可能です。使用者は、リスクに備えておくことができるのです。
いかに裁判所といえども、法律を無視して裁判をするのは問題ではないかと考える人もいるかもしれません。
しかし、裁判所は、法律を完全に法律を無視しているわけではありません。最高裁は、使用者の求償権の行使が、民法1条2項に規定されている「信義則」によって、制限されると判断しました。信義則は、法律を形式的に適用すると不当な結論となる場合に、結論の妥当性を図るための条項です。裁判所は、民法1条2項に従って、裁判を行ったということができます。
具体的には、事案によって異なるものの、0%~25%程度の求償が認められることが多いようです。信義則が結論の妥当性を図るための条項であることから、従業員が実際に支払うことができる程度の金額に落ち着くことが多いようです。